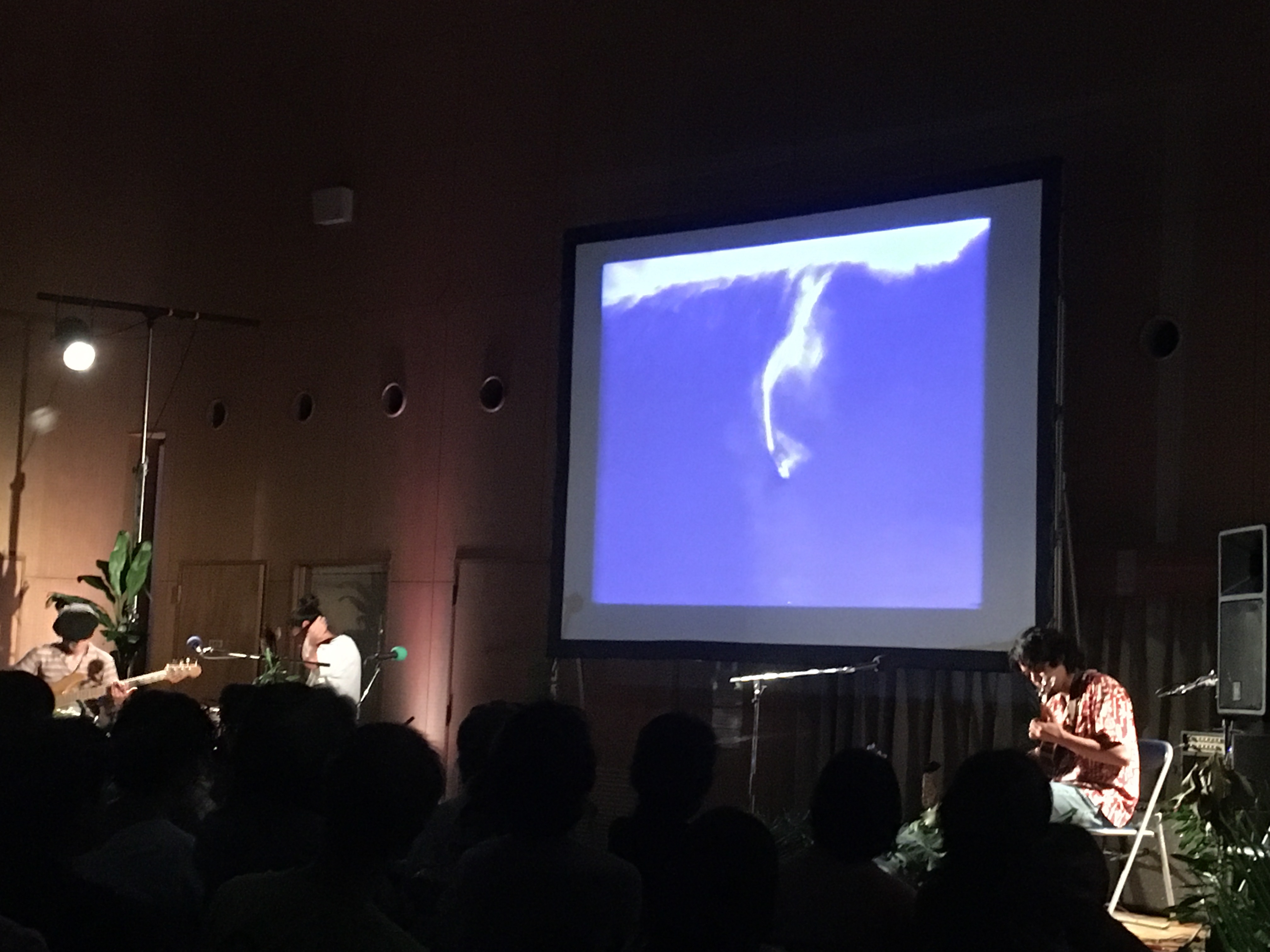小笠原神社例大祭

7月26日、扇浦に鎮座する小笠原神社の例大祭が執り行われます。
この1日だけは貞頼さんも御魂を氏子さんたちによって神輿に移され、狭い神社を飛び出して近くを練り歩きます。
お祭り愛好家の方が十数年前に拵えてくれた木製の御神輿。
なぜ木でできているかというと、ここのお祭りはみんなで御神輿を担いだまま海に入っちゃうのです。
激しく担ぎ海に入るので満身創痍の御神輿ですが、出立前には色とりどりの島の花で飾り付けされて、とても華やかです。
扇浦青年団というこじんまりした集まりで、毎年準備から挨拶などその他たくさんの雑務をボランティアでやっています。
街のはずれにあるこの小さな神社の歴史を紡いでいくために、毎年楽しみに担ぎに来てくれるお祭り野郎のために。
地元の浜降祭に中学1年生から参加して、お祭りの引きつける力にすっかり魅了されて、この年まで元気に担いでいます。
島のために自分ができること、それはただただ元気よく担いで、貞頼さんのご加護が地元の隅々まで行き届くように願うこと。
観光客も含め誰でもいつでも担いでいいオープンなお祭りで、昼時には絶妙な味付けの亀煮とこだわって炊いた赤飯のおにぎりが振舞われます。
島の楽しみのひとつとして、予定に入れてみてはいかがでしょうか?
2025年06月17日 10:25